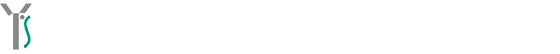Owner
多田貴将(ただ・よしまさ)
Mt. Fuji Japanese Steakhouse
296 Old Rt 17, Hillburn, NY 10931
日本体育大学大学院在学中に、マウント・フジ・ジャパニーズ・ステーキハウスの創業者・藤田徳明から2代目経営者になることを打診され、2005年に渡米。下積み時代を経て、12年から経営を引き継ぎ現在に至る。趣味はスーツをオーダーメイドすること。
名建築のレストランで日本文化を発信し、お客様の「晴れの日」を演出
マンハッタンからロックランド郡ヒルバーンに向かう87号線を進むと、左手前方に山の頂に立つ日本家屋が視界に入る。アメリカでは「ヒバチ(火鉢)」として浸透している鉄板焼きスタイルのステーキハウスだ。戦後を代表する建築様式のレストランで、元オリンピック選手の先代がスタートしたという。歴史と情熱が詰まったレストラン経営の背景と2代目経営者の奮闘とは。
ー ニューヨークで先代が店を構えた背景は。
当店は1969年に創業し、2024年で55周年を迎えました。現在のヒルバーン店は元々、戦後日本を代表する建築家・吉村順三氏が1956年に設計した「モーテル・オン・ザ・マウンテン」という山頂のホテルでした。それを78年に創業者の藤田徳明・一枝夫妻が山ごと購入し、数年にわたる改修を経て「マウント・フジ・ジャパニーズ・ステーキハウス本店」として営業を始めました。吉村氏が手がけたこのホテルは、57年8月発行の「ライフ誌」で「建築の美学」として特集されるほど、50年代を象徴する和洋折衷のモダンな建物です。京都の清水寺のような入母屋造りで、「きわめて日本的な意匠」がレストランおよび、当時あった宿泊施設の様子とともに写真付きで紹介されています。ちなみに、アメリカに現存する吉村氏の建築は、マンハッタンのジャパンソサエティー、ニューヨーク近代美術館(MoMA)から移築されたフィラデルフィアの松風荘、ニューヨーク郊外のロックフェラー別邸などがあります。 創業者で義父の藤田は徳島県出身で、日本体育大学を卒業後、64年の東京オリンピックにレスリング日本代表選手として出場しました。その後渡米し、69年に1号店を開業。ニューヨーク州ロングアイランドやニュージャージー州、コネティカット州などに最大9店舗を構えて、「ヒバチ」スタイルのステーキハウスを経営しました。
ー 2代目として経営を引き継いだ経緯は。
2005年に渡米する前、私は日本でアスリートとして活動し、大学院に通いながら高等教育機関で講師もしていました。大学に入学して間もないころ、義父のレスリング部の先輩に当たる大学教授から「ニューヨークに興味はあるか」と声をかけられたのが始まりです。アメリカンドリームを叶えた後輩(義父)がニューヨークで後継者を探しているという話でした。その後も、大学から大学院にかけての7年間で何度も打診を受けましたが、ニューヨークでレストランを経営する自分が想像できなかったので、ずっと断り続けていました。しかし、久々に教授から連絡があり改めて義父を紹介されたことから、博士課程が始まるまでの休みを利用して1週間だけ訪問することにしました。不思議なことに、初めて会った瞬間から言葉では言い表せない特別な感覚がお互いにありました。そして、今後の渡米を決断。ここで決めなければ、私の人生は全く違うものになっていたでしょう。「やるか、やらないか。経営者としての決断力」を義父も見ていたのだと思います。 それから義父が亡くなるまでの約8年間、経営者としての心構えから実行力まで24時間365日スパルタで徹底的に叩き込まれました。聞いた話によると、義父から後継者として指導を受けた元オリンピック選手だった方が、「オリンピックに出場するよりも、義父からの指導のほうが大変だ」といって帰国したそうです。義父の指導はそれほど厳しいものでした。 現在は、鉄板焼きと結婚式場、そしてバーラウンジの3つの形態で経営を行っています。特に、結婚式場のスペースを使用した各種イベントは、ビジネスとしてまだまだ伸び代があると感じています。
ー先代との印象的なエピソードは。
義父との初日のミーティングで「日本から携帯電話を持ってきたか」と聞かれました。「はい」と差し出すと、「このハンマーで叩きつぶせ」と言われました。日本とのつながりを一切断ち切り、ここでのビジネスに専念するという義父からの最初の指導でした。これはまだかわいいほうで、同様の出来事は枚挙にいとまがありません。常にスパルタ式の指導でしたが、「今は忍耐の時期だ」と覚悟を決めて日々を過ごしました。そして、義父も私に対して「こいつはどこまで耐えて乗り越えることができるのか」と試していたと思います。お互いに根比べ的なところもありました。振り返ってみると、厳しい指導の裏には深い愛情があったのだと感じています。また、経営者の立場になった今だからこそ理解できることが多くあり、義父母からの指導のおかげで現在の私があります。心からの感謝しかありません。
 常にスタッフ1人ひとりに声をかける多田氏。 「あいさつは信頼関係を築き士気を高めるために重要です」
常にスタッフ1人ひとりに声をかける多田氏。 「あいさつは信頼関係を築き士気を高めるために重要です」
ーニューヨークで飲食業を続ける大変さは。
ニューヨークには、アメリカンドリームを求めて世界中から人が集まってきます。フランク・シナトラの名曲「New York, New York」に「この街で成功すれば、世界中どこでも成功できる。それは自分次第だ」というフレーズがありますが、本当にその通りだと思います。この街で生きていくのは大変なことがたくさんありますが、フェアなところもあります。それは、チャレンジしようとする者にとって、チャンスは平等にあること。何事にも情熱を持って前向きに、自分を信じて挑戦し続けていくことが、このニューヨークで成功するための条件の1つだと思います。大変さも含めて日々サバイブできていることに、やり甲斐を感じています。
ー仕事において心がけていることは。
まず私たちのレストランでは、「心を満たす仕事」を大切にしています。ただ料理を提供するだけではなく、お客様が訪れた際の感動を誰かに伝えたくなるような「特別なおもてなしと体験」をお届けすることです。アメリカで学んだフレンドリーなサービスと、日本の細やかな気配りを融合させたおもてなしを目指し、お客様1人ひとりの期待を超える感動を生み出すために日々精進しています。 さらに、お客様には日本の文化や食べ物を「日本ではこうだから」と押し付けないようにしています。その国の慣習や食文化に合わせてカスタマイズすることが、海外での成功と継続のキーポイントだと考えています。そのため、新しいメニューやサービスを常に追求しています。もちろん、日本の本物の良さも伝えていきたいと思っているので試行錯誤の毎日です。 また、「スタッフとともに行動で示す」ことを大切にしています。大雪が降れば一緒に雪かきをするなど、庭園を含め敷地全体のメンテナンスもともに行っています。バックグラウンドや文化、宗教が異なる15カ国以上の国籍を持つスタッフたちをチームとしてまとめるうえで、コミュニケーション能力やリーダーシップを発揮するには、現場主義のアプローチが効果的だと感じています。
ー55周年を迎えて思うことは。
まずは「感謝」です。これまで長い間ごひいきにしてくださったお客様、これからご来店いただくお客様、創業当時から関わってくださっている業者の皆様、そして今もハードワークに励んでいるスタッフとその家族、さらに創業者である義父母。すべての方々のおかげで、現在のマウント・フジ・レストランがあります。最近では、お客様から「私は子どものころからこのレストランに通っていて、今は子どもや孫を連れて家族の誕生日をここでお祝いしていますよ」といった話を聞く機会が増えました。世代を超えて通ってくださる方が多くなったことも、先代から受け継いだマウント・フジ・レストランというブランドが誇るべきレガシーの1つだと感じています。次の世代に引き継ぎ、そして100周年につなげていくために、これからも努力を重ねていきます。
ー過去の経験からレストラン経営に活かされていることは。
大学時代にライフセービングに出会い、「人は鍛えれば鍛えるほど強くなれる。そして強くなればなるほど、優しくなれる」という言葉を学び、日々トレーニングを積んでいました。この経験が、現在の経営者としての立場やホスピタリティー業に携わる者として多くの場面で活かされています。例えば、レストラン営業中に停電や自然災害、お客様・従業員の人的アクシデントが起こった際も、落ち着いて指示を出し対応することができていると思います。内心は焦ることもありますが、「大丈夫だから、落ち着いて」と周囲に伝えて冷静に行動できるのは、ライフセービングの経験のおかげだと感じています。
 夏祭りでは自身も着物を着用し参加する(写真提供)
夏祭りでは自身も着物を着用し参加する(写真提供)
ー今後の目標は。
さまざまなイベントを主催していますが、その1つに4年前から続けている夏祭りがあります。アメリカ在住の日系人や地元コミュニティーの方々に日本文化を体験してもらい、民間レベルでの国際交流を促進し、相互の理解と友情を深めることを目指しています。さらに、アメリカで活躍する日系のシェフやパフォーマーの素晴らしい技の披露を通じて、日本食や伝統芸能をお客様に楽しんでいただくと同時に、母国・日本への誇りを感じてもらえるような時間と空間を提供しています。また、お客様からは「宿泊施設があれば最高だね」という声もあるので、将来は部屋数は少なくても日本スタイルのおもてなしが提供できるホテル「マウント・フジ旅館」をつくれたらいいですね。これからも、体験型の日本文化を発信し続ける場所として、お客様の「晴れの日」を演出していきたいと考えています。
Interviewer: Akiko Takeuchi
Photographer: Masaki Hori
2024年8月30日取材

▼本誌掲載
ニューヨーク便利帳 Vol.33