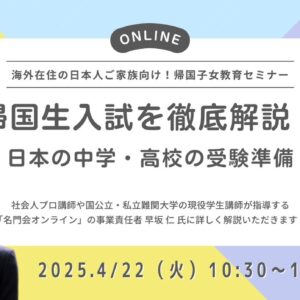President
東 浩(あずま・ひろし)
shibaura-machine.com
755 Greenleaf Ave, Elk Grove Village, IL 60007
1960年生まれ。85年慶應義塾大学経済学部卒、同年東芝機械入社。89年のタイ現地法人設立に伴い、同社初代社長に就任。98年から2002年にかけて北米の射出成形機代理店管理のため東芝機械アメリカに出向。射出成形機事業部輸出部長やインド現地法人(現芝浦機械インド)の取締役を経て19年、2度目のアメリカ駐在を開始。20年から現職。
メガトレンドを捉えて卓越した技術革新で対応
2024年に創立50周年を迎える、産業用機械大手の芝浦機械(旧 東芝機械)。同社の製品が一般消費者の目に触れることはほとんどないが、自動車や家電、医療機器など、実際は身の回りのさまざまなモノの製造に関わっており、誰にとっても身近な存在といえる。
ーイリノイ州に進出した経緯は。
中西部は産業の集積地です。私たちにとって自動車業界が一番の大きなターゲットであり、お客様に近いところを目指し、1974年に北米に進出しました。最初は西海岸から進出し、その後中西部という流れです。シカゴはオヘア国際空港というハブ空港があり、交通の便も含めて当地を選びました。
 シカゴ郊外のエルクグローブビレッジにある社屋(提供写真)
シカゴ郊外のエルクグローブビレッジにある社屋(提供写真)
ーメインの商材は。
射出成形機、ダイカストマシン、工作機械の3つです。事業全体の7割ほどを占める射出成形機はプラスチックを溶かして金型内に注入して成形する機械、ダイカストマシンは金属(アルミニウムやマグネシウム)を溶かして金型内に注入して鋳造する機械、工作機械は金属を削って加工する機械です。
ー製造製品の具体例は。
射出成形機だと、例えばスマホのカメラのレンズやイヤホン、家電など、身の回りのさまざまなプラスチック製品や部品を成形して製造します。自動車ならインパネ・コンソールボックスなどの内装部品およびボディーやバンパーなどの外装部品などです。医療関係では、各種機器やカテーテルなどにもプラスチック成形品がたくさんあり、最近だとCOVID-19の検査キットもそうですね。昨今のカーボンニュートラルの流れで、油圧駆動ではなく当社が主力としている電動駆動の射出成形機のニーズの高まりが小型・大型問わず加速しています。
自動車の量産や軽量化に必要なエンジンやフレームといった金属部品(アルミニウムやマグネシウム)は、ダイカストマシンで生産します。鋳造品の品質向上と大型化に対応するために溶けた金属を素早く金型へ流し込む超高速射出が必要で、その加速度はスポーツカーの100倍の100G、反応の速さは瞬きの時間0.3秒の30分の1と超高速です。射出成形機やダイカストマシンでは、軽量化しながら強度も備えた部品を生産する技術をさらに磨いていきます。 工作機械で切削するものには、自動車部品用の金型、航空機のエンジンやランディングギア、ガスや水力のタービンや建機・鉱山機械向けアームなどのワーク(切削対象の部品)があります。弊社の場合はワークを載せるテーブルサイズが1メートル前後のものから10メートルを超える規模の大型機を得意としています。
一般の消費者が私たちの仕事を直接目にすることはないでしょうが、身の回りのさまざまな部品、製品に私たちの技術が関わっています。

プラスチック製品の成形に使用する全電動型射出成形機(EC-610SXⅢ機)(提供写真)
ーコロナ禍での変化は。
部品や半導体不足が起こり、自動車産業全体が一時止まってしまいました。そのときに起こったことが、コロナの検査機器を含む医療関連での特需です。そしてその後に訪れたのが「巣篭もり需要」。消費者がネットで買い物をするわけですが、例えば衣装ケース、食器、コーヒーメーカーなど、家で使う製品はプラスチックだらけのため、とにかくプラスチック製品の需要が伸びました。弊社は自動車向け製品が主ですが、コロナ禍で医療関連や家庭用雑貨関連がそれを上回ったのです。現在は落ち着いて元に戻りましたが、大きな変化でしたね。
ー自動車業界の今後の見通しは。
自動車業界はコロナ禍での停滞から巻き返すべく、各メーカーがEV(電気自動車)を含めこれからどんどん生産していきます。それに合わせて私たちも新しい投資をしていかなければなりません。EVの航続距離向上のためには、構成部品の軽量化への対応は継続的な大きなテーマで、射出成形機とダイカストマシンではその対応に今後も取り組まなければなりません。
EVについては、製造過程で排出されるCO2の削減など課題も明るみに出てきていますので、EV一辺倒ではなく、選択肢の1つという扱いになってきています。ただ、カーボンニュートラルを考えたときに、原料調達・製造・使用・リサイクル・廃棄まで環境へのインパクトを考えなければならず、最終的な製品だけが良ければいいわけではないと社会全体が気づき始めているので、これからどういう方向に進むかを慎重に見極めていく必要があります。企業は次に何が起こっても対応できるようにしておかなければなりません。そんななかで弊社は、ひとつの方向しかないという前提で決め打ち的にビジネスをするのではなく、グローバル製造業が直面するメガトレンドを捉えて卓越した技術革新でどう対応するかが、結果的に企業価値向上と社会貢献の両立につながると思っています。
地政学的な現象やコロナのパンデミックなど、何らかの要因で急に業績が落ちることもありますが、そうなっても困らないよう、情報に対して機敏に動き、次はどうするかを絶えず考える。装置機械メーカーも例外ではないと思います。
ーアメリカでの社員教育については。
アメリカでは販売とアフターサービス、一部組み立てを行っており、その人材教育に力を入れています。また、2022年からはスキルドワーカー(熟練技術者)不足を補うため、新たな取り組みも始めました。まだ経験の浅い技術者がお客様のところに行っても、リモートでスキルドワーカーと連携してきちんとプロの作業ができるという環境をつくったのです。このサービスを実現させるための教育として、スキルマップを作成してレベルアップを図り、同時に個人個人にも目標を立てさせました。今後も、決まった仕事に対してどう取り組んでいくかを教育プログラムとして確立していきたいと思っています。
ー仕事で心がけていることは。
1989年にタイ現地法人の社長に就任した当時、責任者として雑務を含むさまざまな業務を自分でやらなければいけなかったため、自然とひとつのことを突き詰めるよりも責任者としてどう立ち回るべきか、を考えるようになりました。その経験から、自分がいつそこからいなくなっても効率よく業務がまわるような仕組みを構築することを常に心がけています。海外では特にこの仕組みづくりが重要だと思っています。
その他には、メガトレンドに対応するためのレールを整えていくことや、デジタルサービスを充実させて業務効率を上げることも常に意識しています。2022年に「machiNetCloud」というインダストリアルIoTのデジタルサービスを開始しました。デジタルサービスについてはこれまでも課題としてありましたが、コロナのパンデミックをきっかけに、みんなが「この方向だ」と気づき、ようやく形になったという感じです。

「メガトレンドを把握するためには、まずはお客様の声を聞くことです」と語る東氏
ー仕事で最も印象に残った出来事は。
最初にアメリカに駐在していた2000年、大きな案件の引き合いがあり、それに対応するためアメリカ法人が窓口になりました。当然、私1人では対応できませんから、駐在していたエンジニアや日本の技術部などにも協力してもらい、提案を完成させました。その仕事は入札形式で、最終2社のうちの1社まで残ったものの、最終的に入札は叶いませんでした。ただ、先方のエンジニアチームが「よくここまでやってくれた」と弊社の技術対応力をとても高く評価してくれたのです。その引き合いを経験したおかげで次に役立つヒントをたくさん得られましたし、その後の開発にもすごく役立ちました。営業的にはもちろん残念な結果でしたが、ある意味で達成感がありましたね。
ー今後のミッションは。
おかげさまで、2024年3月期の目標であったグループ売上高1,350億円は、23年12月時点で大きく上回る見込みです。中国、インドと並んで北米市場の期待値も高いため、コロナ後の対応やメガトレンドへの対応をしながら、北米の売り上げをさらに増やしていくことが今後のミッションです。基本的に付加価値が高く難易度が高い工作機械は日本で製造し、標準的な量産できる成形機は海外の工場で製造するというポリシーに変わりありませんので、北米でもこれらの事業はまだまだ伸ばしていきたいです。
Editor: Miho Kanai
Photographer: Masaki Hori
2023年1月13日取材
※「シカゴ・デトロイト便利帳Vol.20」に掲載した内容を再編集して掲載
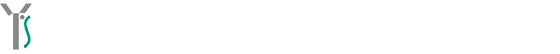

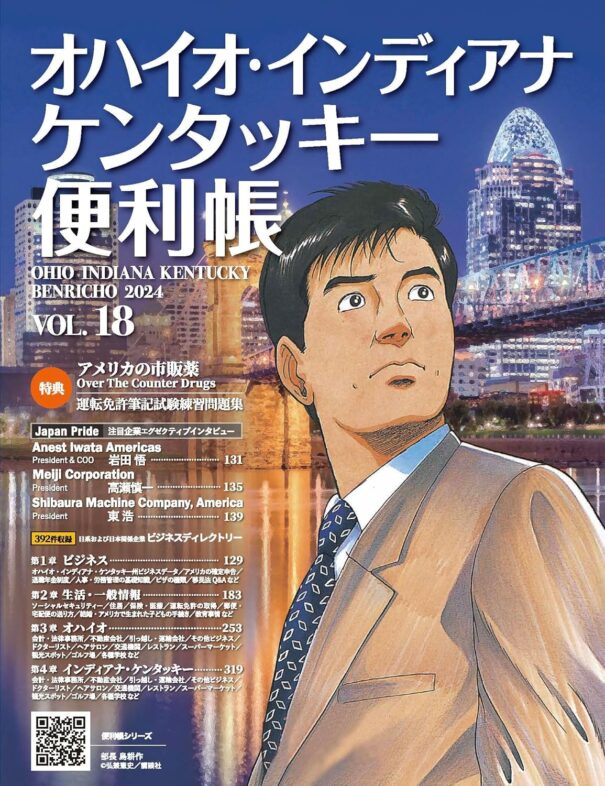 ▼本誌掲載
▼本誌掲載