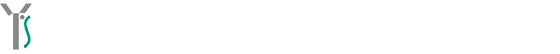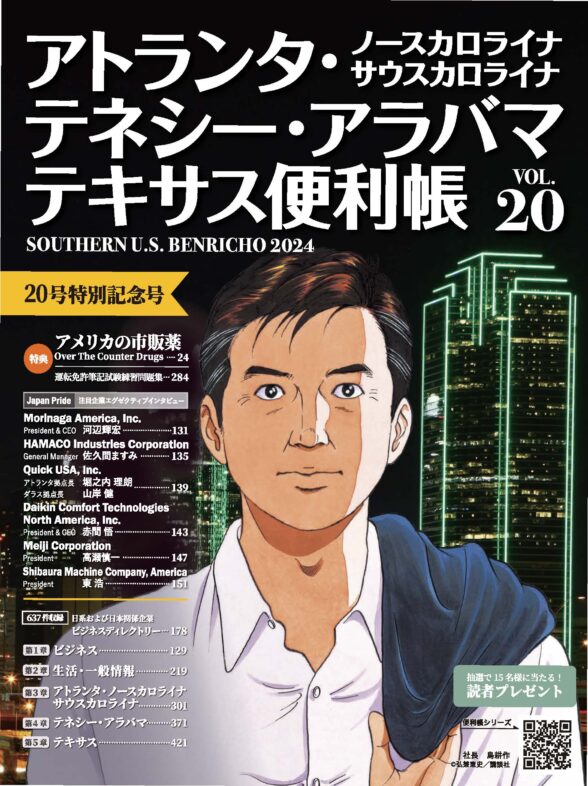President & CEO
赤間 悟(あかま・さとる)
Daikin Comfort Technologies North America, Inc.
Daikin Texas Technology Park, 19001 Kermier Rd, Waller, TX 77484
日本の空調機器のパイオニアであるダイキン。テキサス州ヒューストンに、北米で3番目に大きい製造工場を持ち、アメリカの気候と住居スタイルに合わせた空調機器を年間約500万台生産・販売する。省エネ技術力を生かしたものづくりと日本企業の優れた工場運営能力をもって、北米の空調業界で売り上げナンバーワンを目指す。
人と地球にやさしいものづくりにこれからも取り組んでいきます
日本の空調機器のパイオニアであるダイキン。テキサス州ヒューストンに、北米で3番目に大きい製造工場を持ち、アメリカの気候と住居スタイルに合わせた空調機器を年間約500万台生産・販売する。省エネ技術力を生かしたものづくりと日本企業の優れた工場運営能力をもって、北米の空調業界で売り上げナンバーワンを目指す。
ーアメリカ進出の経緯は。
最初に北米市場へ進出したのは1981年で、アメリカの大手空調キャリアの元社員が営む代理店との提携による輸入販売から始まり、次に熱交換器の企業と合弁し、生産を行いましたが、販売が伸びず撤退。3度目の正直で、2004年にダイキンACアメリカズ社を設立し、住宅用・業務用空調機器の輸入販売を実施しました。「ライバルであるアメリカ企業のホームグラウンドであり、世界で最も難しい市場を攻めるからには絶対にナンバーワンを取る」という当社経営トップの強い意向を受けて、07年にビルや工場に設置する大型の空調機器を納入するマッケイUS社を傘下に持つOYLインダストリーズ社、12年には住宅用空調機器の大手グッドマン社と、2つの大型買収を実行して、本格的にアメリカの空調事業へ参入しました。
ダイキンが得意とする日本のルームエアコンは、各部屋に室内機と室外機を設置する個別空調システムです。一方で、アメリカの住宅用空調機器は、1台の室内機と室外機で冷やしたり温めたりして、空気をダクトで各部屋に送るセントラル空調システムが主流。ダイキンはこのようなアメリカのスタンダードな商品を持っていませんでしたが、開発・生産・供給だけでなく物流も含めてアメリカで高いシェアを占めるグッドマン社を買収することによって、事業が一気に拡大しました。
 「日本人の思いやりの姿勢が工場運営に生かされています」と赤間氏。日本のものづくりのノウハウとグローバルな視点で事業拡大を目指す
「日本人の思いやりの姿勢が工場運営に生かされています」と赤間氏。日本のものづくりのノウハウとグローバルな視点で事業拡大を目指す
ーグッドマン社との事業統合による手応えは。
アメリカの空調市場は特殊で、日本とは異なる空調機器の商品開発から販売までをゼロから開拓することはやはり不可能です。単純に生産といっても材料となる鉄板の調達や部品開発など工程は幅広く、販売においては、卸売り業者を通して建築会社やユーザーに届けるための広大なアメリカの流通網が必須。そこで、これらの課題を既にクリアしているグッドマン社と手を組んだことが、北米展開の大きな足がかりとなりました。
17年にはテキサス州ヒューストンに、グッドマン社が保有していた4工場、本社、物流拠点を統合し、住宅用・業務用空調機器、暖房機器などを生産するダイキングループ最大規模の工場ダイキン・テキサス・テクノロジー・パークを設立。22年には、社名をダイキン・コンフォート・テクノロジーズ・ノースアメリカ社に変更しました。統合に当たっては、国や企業文化の違いに戸惑うこともありましたが、コロナ禍での供給問題などさまざまな課題をともに乗り越えていくなかでチームワークが醸成され、今では全社一丸となって更なる事業拡大に取り組んでいます。
ダイキンの工場は、ボーイング、テスラに次ぐ北米で3番目に大きな製造工場で、敷地は200万平方メートルほどあり、東京ドーム43個分に値します。約8,000人の従業員が働き、年間約500万台の空調機器を生産。亜熱帯から寒帯まであるアメリカの気候に合わせるため、機種数が非常に多くなりますが、それらを含めてここの工場で賄っています。米州地域(中南米含む)の売上高は、過去10年間で3.6倍に成長し、今やダイキングループで売上トップの地域に成長しました。
ーその他グループ会社の事業内容は。
まずダイキンアプライドアメリカズ社(DAA)は、工場やビルなど大型空間に適応する業務用アプライド空調機器(チラー、エアコン、ファンコイルなど)の製造と販売およびサービス、ニューヨークとワシントンDCに事務所を構えているダイキンUSコーポレーション社は、主に環境負荷が低い空調機器の普及に向けて、国際的な規制やルールづくりのためのロビーおよびアドボカシー活動に務めています。アメリカン・エア・フィルタ社(AAF)は、空調機器に欠かせない空気浄化や集じんを行う住宅用・業務用フィルターの製造と販売を行っています。
そして、空調に関連する事業の他に、フッ素化合製品の研究・開発・製造・販売も行っています。家庭用品や自動車などあらゆる産業分野で活躍するフッ素化合製品ですが、ダイキンは独自の技術をグローバルに展開しています。ダイキンアメリカ社(DAI)では、上記フッ素化合製品の製造・販売のみならずフランスの大手化学メーカー、アルケマ社との契約の下、エアコンの冷媒の調達などを行っています。
ーダイキン製品の強みは。
快適で省エネな運転を行うヒートポンプとインバータは、どちらもダイキンが持つコア技術です。まず、空調製品の基本であるヒートポンプ技術ですが、例えば、100Wで空気中にある熱を回収し、冷凍サイクルにうまく取り込んで熱を放出すると300Wのアウトプットが得られます。これは冷・暖房どちらにも使える技術で、EUでは再生可能エネルギーとして認定されています。またインバータ技術は、エアコンの心臓である圧縮機のモーターを止めることなく、周波数を変換させて連続的にコントロールすることで、高パワーで室内を素早く冷暖し、その後は低パワーで快適な室温に保つことができます。圧縮機の運転がオン・オフを繰り返さないため、電力消費に伴うCO2削減になり、ノンインバータ機と比べ電気料金を低く抑えることが可能です。
日本の住宅用におけるヒートポンプとインバータの普及率は100%ですが、北米ではまだ3%程度しかありません。加えて、電気の消費はその土地の気候や地域性によって変動し、各住居システムにも左右されます。いまだにアメリカでは大きな一戸建ての暖房に、効率や省エネ性が非常に低いガスや電気ヒーターを使用しているのが現状です。こうしたなかで、ダイキンはどのような地域にも適した幅広い品ぞろえで、空調のニーズに応えられることが強みです。
ー環境問題については。
通年エネルギーの消費効率を表す指標として期間エネルギー効率(SEER)というものがあり、この指標で見るとアメリカは先進国のなかで1番遅れています。この要因として、やはりインバータ化の遅れが挙げられます。また、パリ協定では25年までにCO2排出量ゼロを目指す目標値を掲げており、それを支援するためのインフレ抑制法(IRA)のなかで、脱炭素化を推進していくための事業や商品に対してインセンティブが多数含まれています。これを受け、ダイキンは、環境負荷を減らしながら使用できる空調機器の普及を図っています。
加えて、アメリカ環境保護庁(EPA)は冷媒ガスの使用量・生産販売量を段階的に削減することを決定し、25年から規制が開始されます。この冷媒ガスは温室効果ガスの1つで、ダイキンは温暖化係数が低い冷媒技術の採用を進めています。これからも、環境団体やNGO、電力会社など、さまざまなステークホルダーの方々と連携を取りながら、グローバルな環境問題の解決と社会の持続可能な発展に取り組んで行きます。
ー海外でビジネスを行うことについては。
日本で培ってきた技術や製品の他、マーケティングのノウハウを現地に合わせながら、社員ならびに幹部と一緒に事業の拡大に邁進してきました。また、アメリカの事業は単独ではなく、日本の親会社と連携しながら独自の「FUSION(フュージョン)経営」を行っています。戦略を実行して成果を出すための具体的なアクションを5カ年の計画で考え、この国の事業をどのように進めていくのか、地域戦略を策定しています。
そして、「人を基軸におく経営」がダイキンの基礎です。海外で実感することは、ホスピタリティーという言葉とは違う、日本人が持っている思いやりの姿勢が仕事をしていくうえで非常に重要だということです。例えば、工場運営の基礎である整理整頓・清潔については、ごみをポイ捨てせず、汚したものは自分たちで掃除する、その心構えが大切です。アメリカの分業体制ではない、人と人のリレーションシップから始まり、部門と部門、会社と会社がいかにつながっていくのか。お互いが協業することで、より良い商品の開発ができます。それは、商品開発のスピードやコストにも反映されることです。
ー今後の目標は。
25年には北米の空調業界で売り上げナンバーワンを目指します。ですが、これは1つのKPI(重要業績評価指標)だと思っています。私たちは建物そのものには直接携わっていませんが、空調機器の開発・製造・販売を通じて、この国の方々の生活をより豊かにしていきたいと思っています。そして、省エネ型
で脱炭素化に向けた空調機器を供給していくことも目標です。そのために、人と地球にやさしいものづくりにこれからも取り組んでいきます。
また、北米で構築したビジネスモデルを母国・日本に還元したいと思っています。有形・無形の財産をいかにフィードバックできるのか、日本人としてそのように考えながら、事業の成長と社会への貢献に努めていきます。
Interviewer: Akiko Takeuchi
2024年4月3日取材