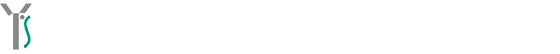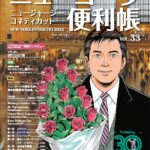Principal
眞壁 光(まかべ・こう)
Kohn Pedersen Fox Associates PC
11 W. 42nd St, New York, NY 10036
1971年生まれ。二十歳で渡米し、97年オクラホマ州立大学建築学士号取得、同年KPF入社。ニューヨークを拠点に世界各地の不動産開発プロジェクトに携わり、建築デザインを手がける。アメリカ建築家協会会員、イギリス王立建築家協会会員、オクラホマ州立大学建築学部アドバイザリーボードメンバー、ハーバード大学建築学部講師などの肩書きを持ち、アメリカ建築家協会賞をはじめ受賞歴多数。2012年から現職。
住む人と訪れる人、みんなが心地良く過ごせる空間を創造
世界的な建築事務所、KPFで日本人唯一のプリンシパル(代表)を務める眞壁氏。ラスベガスのマンダリン・オリエンタル・ホテルやマンハッタンのアンダーズホテル、東京のコレド日本橋や福岡のワンビル(2025年1月開業)など多数の有名建築デザインを手がけ、アメリカはもとより欧州、中東、インド、中国など世界各国の要人からも信頼の厚い建築家だ。
ー 海外に出たきっかけは。
大学進学のため、二十歳のときに渡米しました。実は小学生のときからずっとアメリカに来たかったのですが、私が生まれる前からアメリカに住んでいる叔父から、「日本人のアイデンティティーは残しなさい」と言われていました。だから、「高校より前にアメリカに来てはいけない」と。叔父は非常に面白い経歴を持つ人で、高校卒業後に米軍基地で働いていましたが、そこのトップの人の紹介でアメリカにホームステイすることになり、アメリカの大学卒業後、がむしゃらに働き日米の鉄鋼業会社からヘッドハンティングを2回されるほど実績を上げ、今は日系商社のアドバイザーを務めています。私の人生が彼の影響を受けているのは間違いありません。

建築家としてキャリア27年の眞壁氏。「今は日本人の留学生が減っていますが、もっと若者に夢を持ってもらえるよう、子ども向けの 講演会などもやってみたいですね」
ーKPFに入社した経緯は。
オクラホマ州立大学在学中の1996年にKPFのインターンシップに参加しました。インターン期間中に六本木ヒルズの打ち合わせのため当時の森ビルの社長・森稔さんたちがニューヨークにいらっしゃった際、日本語ができるからと通訳を頼まれ、その仕事を通してKPF創設者のビル・ペダーセンや当時の社長である故ポール・キャッツから少しずつ信頼を得るようになりました。彼らから大学卒業後に戻ってきなさいとオファーを受け、97年に入社しました。ビルと彼の奥さんと一緒に京都に行ったり、現場の視察に同行したり。私にとってビルとポールはメンターです。彼らは世界各地で案件を取るたびに私を連れて行ってくれて、そこでさまざまな人と出会い、次第にデザインも任せてくれるようになりました。ビジネスをする上で人とのつながりはとても重要であり、ありがたいことに私の場合は早い時期から人に恵まれていたと思います。
ー担当したプロジェクトの例は。
最も規模が大きかったものだと中国・西安の都市開発です。約460万平米ある街全体のマスタープランをつくりました。アメリカ国内だとラスベガスのシティーセンターが有名で、そのなかにあるマンダリン・オリエンタル・ホテルのデザインを担当しました。ニューヨークだとマンハッタンのハドソンヤードのデザインにも関わりました。ハドソンヤードはニューヨークにオリンピックを招集するスタジアムから始め、その後現開発のマスタープランを行い、いくつかの建物を設計しました。その他、5番街のアンダーズホテル(竹中工務店のアメリカ法人TAKが所有)の改装は私のデザインによるものです。建物以外では、高級寿司店のおみやげの文鎮をデザインしたこともあります。規模は関係なくすべての仕事に対して楽しんでおり、中身が新しければ新しいほどワクワクしますね。
ー特に思い入れのある建物は。
どれも思い入れはありますが、特に印象深いのは長野県でデザインした工場です。創設者のビルは「うちは工場のデザインはやっていないから」とやや後ろ向きでしたが、かたやポールは「面白そうだから行って来い」と後押ししてくれました。それでつくったのがINCSゼロファクトリーです。地上階がショールームで、地下に生産工場があります。入り口に真っ直ぐ延びる歩道があり、ファッションデザイナーのコシノジュンコさんがここでファッションショーをやりたいと言ってくれて、結局ショーは実現しませんでしたが、とても面白い仕事でした。
また、2025年開業の福岡のワンビルは、いろいろな意味でとても良い建物だと思っています。建築業界において、なかには設計までは問題なく進んでいても施工の段階で予算が削られてしまい、つくりが粗雑になってしまう物件も残念ながら存在しますが、ワンビルのようにゼネコンと建築事務所、そしてクライアントの想いがきちんとつながってできた建物は、やはり良いものに仕上がります。
ー大型複合施設の開発の流れは。
例えば2020年にマンハッタンに誕生した複合ビル、ワン・バンダービルトの場合は、ミッドタウンイースト全体の開発が背景にあります。開発前のイーストサイドは全体的に活気がなくなっていました。なぜかというと、1960〜70年代に建てられたオフィスビルが多く残っており、それらは天井が低いため現代のオフィスには適さず、需要が減ってしまったからです。そうなると反対にウエストサイドの開発が進みます。その代表例としてハドソンヤードがあり、企業がそちらに進出すると住居もそれに続く、という流れでウエストサイドに人や物が集まるようになっていきました。そこで、イーストサイドの活気を取り戻すためにディベロッパーが何をするかというと、開発がしやすくなるようにニューヨーク市にゾーニング(土地利用規制の区域分け)を変えてもらうよう働きかけるのです。ワン・バンダービルトはそのプロジェクトの一環であり、グランドセントラル駅に直結し、さらに同駅にロングアイランド鉄道が乗り入れるようになったため、ロングアイランド方面の人々もミッドタウンに来やすくなりました。このように、人の流れをつくり街自体を変えることを事業の目的として開発計画が行われます。
ー計画実行において重要なことは。
建物のデザインと並行して、採算が取れるかどうかコストの計算も行います。特にニューヨークや東京、ロンドンなどの洗練された都市は開発に関わる人たちの考え方もしっかりしているので、形さえかっこよくできればいいという話ではなく、事業性があるかどうかも厳しく評価されます。六本木ヒルズの森ビルを手がけたときもそうでしたが、以前は低層の住宅しかなかった六本木に複合施設を開発するにはさまざまな意見があり、説明会を何度も重ね、住民を説得する必要がありました。単に移転を迫るのではなく、地権者の皆さんが六本木ヒルズのレジデンシャルに移る権利があることや、開発によって利便性が高まり、生活環境が良くなることを熱心に伝え続けました。人々が使いたいと思える場所をつくることで地域貢献ができるということを説明し、地域の人々に納得していただければ開発を実現することができます。
ー開発に要する時間は。
六本木ヒルズの例だと、完成までに20年ほどかかっています。私たち建築家がプロジェクトに本格参入する前から、構想におそらく10年はかかっているでしょう。私たちが関わったのは全体のうち10年ほどです。プロジェクトにもよりますが、ああいう大規模開発になれば長い年月がかかりますし、一方で、中国ではコンペを勝ち取ってから竣工まで3年半というものもあります。コロナ前の中国の建設ブームはとにかく目を見張るものがあり、弊社の利益のかなりの比重は中国からでした。その波が過ぎて、今はアブダビやドバイなどの中東圏とインドのプロジェクトが増えています。
ーアメリカの不動産開発の現状は。
昨今、開発需要が多いのはフロリダ州のマイアミ、ウエストパームビーチ、ジャクソンビルや、テキサス州のオースティンなど、レッドステート(共和党支持者が多い州)と呼ばれる地域です。テキサス州にオフィスを移すIT系の企業が増えており、金融系もフロリダ州に移ろうという動きがありました。反対にカリフォルニア州などのブルーステート(民主党支持者が多い州)は、オフィスに限らず開発需要が低くなっているというのが私から見た最近の傾向です。ただ大統領選後にどうなるかは注目すべきところです。
ニューヨークはコロナ禍でオフィス需要が減ったこともありプロジェクト数は少なくなっていますが、住宅需要は増えています。先ほど説明した通り、ミッドタウンイーストには天井の低いオフィス物件が多くありますが、住宅の場合そこまで天井の高さは必要なく、また昔の建物は凸窓が多いため、それらを生かしながら住宅に変換しようというアイデアです。

長野県茅野市にあるINCSゼロファクトリー。自然環境に溶け込むよう、周りの木々を超えない高さにデザインされている(提供写真)
ー次世代建築に求められることは。
一番重要なのは、環境にやさしい建物であることです。環境にやさしいとは、自然に対してだけではなく人に対してもそうです。地球環境に対してサステイナブルであることは欠かせない要素であり、また、そこに住む人と訪れる人、みんなが心地良く過ごせるような、そして子どもたちをそこで育てたいと思えるような空間を創造することが重要です。こういったニーズは時代に合わせて変わるもので、それに対してどう工夫を凝らすかは、私たち建築家が考えなければならないことです。それはオフィスビルであってもそう。昔はオフィスビルに憩いの場はありませんでした。コレド日本橋を手がけたとき、金融系といえばクールなデザインで、エグゼクティブフロアは濃い色を使って高級感を出すのが主流でしたが、今はホテルのような温かさを感じられるデザインに変わってきています。素材も鉄やコンクリートだけではなく木を使うなどの工夫をして、「やさしい」建物をつくるということが1つのテーマになっており、私たち建築家がもっと努力しなくてはならない課題だと思っています。
Interviewer: Miho Kanai
Photographer: Masaki Hori
2024年9月9日取材

▼本誌掲載
ニューヨーク便利帳 Vol.33