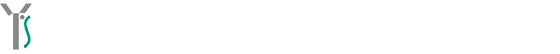Chairman
福田 宏(ふくだ・ひろし)
Central Ohio Japanese Association of Commerce
P.O. Box 340071, Columbus, OH 43234
東京都新宿区出身。法政大学卒業後、1988年日新航空サービスに入社。91年にオハイオ州に駐在し、同年設立されたオハイオ日本人会を見聞。2回目となる同州駐在中の99年、当時のCOJAC会長から任命を受け事務局長に就任。2023年、会長に就任し現在に至る。日新航空サービスでは、24年に取締役を退任し顧問。アメリカ駐在生活は通算30年。趣味はオートバイ。
在留邦人が安心して暮らし、事業を営むための支援を提供
オハイオ州コロンバスを拠点に活動するオハイオ日本人会。設立から30年以上にわたり、在留邦人のライフラインを支え、日本人同士の交流31の場を提供してきた。事務局長および会長として26年間運営に携わってきた福田氏に、これまでの歩みと今後の展望について聞いた。
ー オハイオ日本人会とは。
オハイオ州コロンバス地区を中心とする非営利の日本人会です。在留邦人が安心して生活・事業を営めるよう、ライフラインを支える重要な役割を担っています。オハイオ州には日本国総領事館がないため、総領事館からの連絡網を受け持ち、日本とのつながりを維持する活動に注力しています。また会員相互の親睦を図るために 、レクリエーション行事としてゴルフ大会・ボウリング大会・ピクニック・フルーツ狩り・餅つき大会などを毎年開催している他、地域行事にも参加しています。さらに商工会の機能として、各種ビジネスセミナーを主催することで、事業支援や情報交換の場を提供しています。

餅つき大会は、世代を超えて毎年多くの参加者が集う(提供写真)
ー設立の経緯は。
50年ほど前まで、オハイオ州では日系企業や在留邦人をほとんど見かけませんでした。しかし、1970年代にホンダが進出したことを契機に、80年代には多くの日系企業がセントラルオハイオに拠点を設け、それに伴い日本人の数も急増しました。異文化のなかで新たに生活と商業を営むうえで日系企業間での協力の必要性が高まり、91年2月に43社の企業が集まりオハイオ日本人会が設立されました。
ー具体的な取り組みについては。
会員同士の交流や日本文化の体験を目的に、季節ごとのレクリエーション行事を開催しています。なかでも500~600名が参加する餅つき大会は大変人気です。当日は50~60名のボランティアスタッフの協力で運営され、世代問わず誰もが楽しめる催しとなっています。日本でも餅つきを見る機会が少なくなりましたが、毎年大勢の方に参加していただき、地元住民の方々からも好評を博しています。つきたてのお餅は、からみ・あんころ・きな粉・納豆などの味付けにしてその場でいただくことができ 、賑やかな1日となります。
加えて、家族で参加できるピクニックやフルーツ狩りもとても好評です。ピクニックはコロンバス動物園のなかにある会場を貸切って開催しますが、ランチを提供していろいろなゲームを催す他、参加者は自由に園内を見て回ることができます。9月はチェリーホークファームでリンゴ狩りをしました。ゴルフ大会は主に男性の参加者が多いのですが、企業の垣根を越えて交流する貴重な機会を提供できていると実感しています。このような行事を通じて、同じ環境にいる日本人同士が情報を共有し、助け合う構図が自然と生まれていると感じています。これらの開催費用は会員費で賄われているため、ゴルフイベント以外の参加はすべて無料で楽しんでいただけます。
また、オハイオ州は在デトロイト日本国総領事館の管轄区域にあるため、領事出張サービスを通じて、旅券交付や各種証明書の発行などのサポートを行っています。2024年11月には330件以上の手続きが行われ、当地の日本人には重要な支援となっています。今後もこのサービスが領事館との協力のもと継続して提供される予定です。さらに、労務・雇用・法規・税務など会社運営に欠かせない多岐にわたる内容を取り扱ったビジネスセミナーも開催しています。これまでに、中西部に拠点を置く日系企業や会計・弁護士事務所などと共催で実施してきました。コロナ禍ではすべてオンラインで開催していましたが、24年後半からは対面式に戻したセミナーも再開し、再び需要が高まると予想しています。
ーこれまで最も印象に残っている出来事は。
過去には日本から著名人やエンターテイナーをお招きして大規模なイベントを開催したこともありました。しかし、改めて私たちの役割を実感した出来事は、新型コロナウイルスが蔓延した2020年のことです。感染者数の増加、外出禁止令、勤務体制の制限など、市や州からの通達が不規則かつ突然に発せられる環境下で、在留邦人にとって情報の把握は非常に困難でした。特に、多方面から日々寄せられる膨大な英文情報を正確に理解することは容易ではありませんでした。そこで、総領事館から毎日送られてくるオハイオ州の日本語の最新情報を、4カ月以上にわたって毎朝欠かさず会員に配信し続けました。国家緊急事態宣言が発令されるなかで、生活やビジネス運営に関わる重要な情報をいち早く在留邦人に届ける必要があったからです。この経験を通じて、当会の役割である「在留邦人のライフラインを支える」という原点を深く受け止める機会となりました。
ー会長として心がけていることは。
まず活動に関しては、設立から30年以上が経過していますが、常に進化を続けることが必要です。しかしその進化が 、長年アメリカに住み 、地域に慣れ親しんだ方々向けの活動に偏ることがないよう意識しています。当地に住む日本人の多くは日本から派遣された駐在員とその家族であり、滞在期間は3~5年が一般的で、海外生活が初めての方も毎年多いことが現状です。日本から移住してきたばかりの方々のライフラインを支えることを忘れず、時代や環境の変化に合わせた活動を行い、次世代につなげていきたいと思っています。
次に運営ですが、事務局を含め専任の職員を置かず、全員が本業を持ちながらボランティアとして活 動を行っています。これは、北米における同規模の日系団体としては珍しい体制だと思います。地域の事業者が業種の枠を超えた「人と人とのつながり」で運営は支えられています。そのため、私は運営スタッフが気持ちよく積極的に協力できる環境づくりを心がけています。駐在員が多い地域特有の事情として運営スタッフの交代も頻繁に発生しますが、引き継ぎを円滑に行うことや風通しの良いコミュニケーションを保つことで、組織全体の連携と発展を促進するよう努めています。
ー長年のアメリカ生活で感じた日米における文化の違いは。
個人的には、協調性と自主性のどちらを重視するかという点が日米の大きな違いだと一番実感していますが、より身近な「時間感覚の違い」について取り上げたいと思います。時間の感覚や概念は、文化的な価値観と深く結びついているといわれます。 例えば、職場において日本人はアメリカ人に対して「仕事の時間を守らない」と思うことがあるでしょう。就業や会議の開始時間を守れず、全員がそろわないことを指摘します。一方で、アメリカ人も日本人が「仕事の時間を守らない」と感じています。それは、始業厳守で終業はルーズである傾向です。就業時間が終わっても職場に残っていたり会議が予定時間を過ぎても継続していたりする光景がしばしば見受けられます。この違いをお話すると日本人は一瞬戸惑いますが次第に納得するようになり、「確かに痛いところを突かれた」と苦笑します。これは両国のビジネスマナーや働き方にも通じる重要な要素だと考えています。当会ではこうした文化の違いをより深く理解する機会として、アメリカ人を雇用する日系企業のマネジメントをテーマに、ビジネスセミナーを開催したこともあります。
ー今後の目標は。
コロナ禍では、地域企業の撤退・統合や経費圧縮の影響で退会する企業もありました。その後も生活環境の変化により、2年以上にわたって活動の制限を受けました。しかし、2024年にはすべての活動を再開し、新たな行事も導入。行事の参加人数もコロナ前を上回る勢いで増えています。これを踏まえ25年度の活動指針として、会員企業の獲得に向けた宣伝活動と地域社会との交流拡大という、2つのプロジェクトを計画しています。まだ検討中になりますが、地元警察からの協力を得て法人向けの安全対策や運転マナーに関するセミナーの開催、自動車産業における技術革新や市場動向の変化から、自治体やカウンティーと連携し日系企業と地元企業が共同して取り組む企画などの実施、そして教育・医療・治安面のさらなる連携を通じた会員や地域住民が住みやすい環境の整備、などを考えています。加えて、地元の主要団体であるワン・コロンバス、ジョブズ・オハイオ、シティ・オブ・ダブリン・エ コノミック・ディベロップメントなど横のつながりを通して協働できればと考えています。引き続き会員の意見や企業ニーズに応えながら、生活と事業の両方を支える活動を進めていく予定です。

「オープンな対話を大切にしています」と語る福田氏
ー入会を検討している企業へ。
約1万人の日本人が暮らすオハイオ州 に お い て 、日 本 と の つ な がりを 保 ち 異国での生活に慣れるために手助けをしていくこと、またお互いに助け合っていくことは、必要不可欠なものと強く感じています。なかでも緊急時や有事の際の敏速な連絡体制を構築していることは、すべての日本人にとって、何かと有益であり、安心をもたらすものと思います。オハイオ州に来られたばかりの方・企業はもちろんのこと、既に事業をされている未入会の方・企業は、ぜひこの機会にご入会していただければと思います。楽しく安心な駐在生活、そしてオハイオ生活の思い出を、ご自身の手で築いていきましょう。皆さまとお会いできる日を楽しみにしています。
Interviewer: Akiko Takeuchi
Photographer: Shizuka Hirano
2024年12月12日取材
 ▼本誌掲載
▼本誌掲載
オハイオ・インディアナ・ケンタッキー便利帳 Vol.19