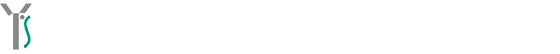ニューヨークのジャパンタウンといえば、まず思い浮かべるのがイースト・ビレッジだろう。渡米から50年、日本食レストラン「波崎」をオープンして34年、以来このイースト・ビレッジを中心にマンハッタンで16店舗の日本食レストランを経営するTICグループの八木社長は、イースト・ビレッジをジャパンタウンとして盛り上げてきた第一人者である。
日本食の伝道師として長年ニューヨークの飲食業界を牽引してきた八木氏にお話を伺うため、9丁目にあるオフィスを訪ねた。
新しいことにチャレンジすることも大事ですが、流行に惑わされずに、原点をこれからも守っていきます
渡米のきっかけを教えて下さい。
私の青年期は、裸足から下駄、下駄から靴、とアメリカ文化の影響を受け、発展してきた時代。そんななか、私は世界経済の中心であるニューヨークにいつか住むことをずっと思い描いていました。
転機となったのは大学進学を考えた時期のこと。当時、実家が波崎であったため、大学入試を受けるためには東京の友人宅に泊まらざるを得ませんでした。ところがその友人の牛乳配達のアルバイトを手伝っていたら試験当日に遅刻をしてしまい、結局テストを受けることさえできませんでした。それをきっかけに、勉強で何かを学ぶよりも、実体験から得ることが自分に合っていると、アメリカ移住を決意しました。それが19歳だった1968年のことです。
今思うとそれが私の人生における大きな第一歩となり、今の私がここにあるのだと思います。もし、大学に進学していたら、また違う人生となっていたでしょう。
渡米直後はどのような生活をされていましたか。
渡米前、アメリカの環境に慣れるために座間市にある米軍キャンプ内で働いたところ、基地内で知り合った兵隊が彼の故郷の街で住む家を世話してくれることとなり、船でアメリカへ渡り、フィラデルフィアのジャーマンタウンという小さな街で「アメリカ」をイチから学ぶこととなりました。頭に描いていた消費大国アメリカのイメージとはまったく違った質素な生活も目の当たりにしました。
私の兄が飲食業を営んでいたため、手始めにレストランで働くことに。レストランでなら手に職がなかった私でも働けたうえに、食事が2度も出る、という大きな理由もありましたが、レストランビジネスの基礎を学ぶことができました。
ニューヨークに来た経緯を教えてください。
5年間のフィラデルフィア生活を経て、アメリカ横断、ヨーロッパ旅行を体験し、日本へ一時帰国しました。日本では露店を営み資金を集め、再び渡米。そしてマーサズ・ヴィニヤード島にある海の家式の焼き鳥店を始めました。そこで得た利益をもとにトラックを買い、次に「YAO-Q」という八百屋をニューヨークで始めたのです。それはレストランに飛び込みで行き、野菜をその場で売るという仕事。何のノウハウもありませんでしたが、1年と経たず店舗を持つまでに成長しました。
卸売り業ではレストラン事業の内部を知ることができたので、1980年には店を改装し、24時間オープンのダイナー「アメリカンダイナー103」を開店し、野菜の卸し売り業と両立させました。野菜の卸しのために夜中の12時に野菜を買い出しに行き、夜のうちにすべて配達し、配達が終わるとレストランで働くという日々で、当時は寝ずに働き続けていました。
イースト・ビレッジを拠点として選んだ理由は何ですか。
当時のイースト・ビレッジは、大使館も危険地区と指定する治安の悪い場所で、観光マップに掲載されないようなエリアでした。コインランドリーで洗濯をしていたはずの服が、気が付けば数時間後には路上で売られていたことも。
それでもこの場所でビジネスをし続けてきたのは、この地ならではのオープンな雰囲気があったからです。もともとここは移民の街で、私自身も裸一貫で来たからこそ、第二の故郷のようにさえ感じます。
日本食のビジネスを始めたのはいつですか。
84年、イースト・ビレッジに日本食レストラン、「波崎」をオープンしたのが最初です。コンフォートフードとして日本食を広めれば、人種のるつぼであるニューヨークのさまざまな嗜好を持った人びとに対して広く訴求できるのではないかと考えました。とくにイースト・ビレッジにはオープンマインドな人が多く、比較的受け入れられやすい街であると感じていました。
ビジネスを始める際は、地域との繋がり、そしてコミュニティーとの関わりを築いていくことが肝要です。地域のために、地域の人たちと一緒に事業を実現したいという思いが根底にあります。

時代の流れを見極め、その時代に合った日本食、つまりTPOに合った食べ物を提供していくことが大切です
当時のイースト・ビレッジの日系コミュニティーはいかがでしたか。
セント・マークスは当時からにぎわっていましたが、波崎のある9丁目は何もありませんでした。家賃は安価でしたが、自ら周辺地域を盛り上げなけなければいけないため、レストランを増やし、自らの手でこの通りを開発していきました。当時3,000人ほどいたイースト・ビレッジの日系コミュニティーのために、1990年からお祭りも企画運営しました。
そのようにして続けてきたことが今では第2世代に受け継がれ、ジャパンタウンといえばイースト・ビレッジというイメージを確立するようになりました。
顧客をひきつける秘訣を教えてください。
我が社のレストランでは最高級を目指すのではなく、常に基本を意識しています。基本とは、自分たちにとって居心地がよく、自分たちが本当に食べたいものを提供できているか、ということ。
調理師免許も持つ美食家の家内が、アドバイザーとして縁の下の力持ちとなってくれていることも大きいです。家内と一緒に頻繁に店舗へ足を運んでキッチンを見たり、スタッフと話をしてコミュニケーションを取り、味のチェックも行うようにしています。
顧客サービスに関していうのであれば、お客さんを楽しませるというのが経営者としてのモットー。拘束時間が同じなのであれば、一生懸命働けば時間も早く感じ、お客さんも喜び、チップも多くもらえる。いい循環を重ね、お店も盛り上げることが、顧客のリピートに繋がります。
多くの店を展開されていますが、共通して心がけていることはありますか。
我々は基本と原点をとくに意識しています。
例えば我々の運営するカレー専門店、「Curry-Ya」では、いわゆる日本の洋風カレーを提供しています。カレーにはそれぞれの家庭の味というのがあるため皆が満足する味を考え、現在の味に行き着きました。日本におけるカレーの歴史は、そもそも日本の大使がイギリスに向かう汽船の中で、インド人シェフの料理を食べたところから始まったといわれています。そうしたルーツにのっとった、万人に愛されるカレーを考えています。
ラーメンに関していえば、終戦後の横浜のバラックにできたラーメン屋がその原型だと考えています。我々のラーメン店「来々軒」では、醤油、塩、味噌という原点、元祖を提供しています。
ミッドタウンの日本食レストラン、「酒蔵」は杜氏と顧客を繋げる役割として、杜氏の気持ちを最も大切にしています。日本酒というものは管理をしっかりしないといけません。並べれば売れるというわけではないのです。

日本食の幅広い人気、そしてその未来をどのように考えていますか。
日本食には計り知れない可能性がまだまだたくさん残されています。
なぜ日本食がここまで広まったかというと、焼く、蒸す、生といった調理法のバリエーションがあり、塩、胡椒、醤油、ソースをはじめとする調味料のバリエーション、それにくわえ、日本人特有の探究心、忍耐力、質の良いサービスがあったからだと考えています。
時代の流れを見極め、その時代に合った日本食、つまりTPOに合った食べ物を提供していくことが大切です。
これからも、まだ紹介されていない日本食を時代にあわせて提供していきます。新しいことにチャレンジすることも大事ですが、流行に惑わされずに、原点をこれからも守っていこうと思っています。
基本があり、それを守ってこそ、いろいろなバリエーションが生まれるのです。
これからの展望をお聞かせください。
老舗としての風格を持って事業を続けていきます。それは原点に戻って、それを守っていくということでもあります。
弊社のモットー、“Enjoy Japan without Airfare”というように、イースト・ビレッジに来ればそこには日本がある、という状態を確かなものにしていきます。
日本食をそのまま持ってきても、必ずしもうまくいくとは限りません。今までの経験を生かし、幅広く、多面的に事業を広げること。私は一生現役でやっていくつもりです。

1948年生まれ、茨城県出身。1968年に渡米。フィラデルフィアのガソリンスタンドやピザ屋で働いた後、ニューヨークで八百屋を営み、84年にイースト・ビレッジにすし店「波崎」をオープン。以来「酒蔵」「しゃぶ辰」「茶庵」「蕎麦屋」「咖喱屋」「来々軒」など、イースト・ビレッジを中心にニューヨークで日本食レストラン16店舗を経営している。
Interview : Takayuki Kawajiri
Photo (Portrait) : Miki Takashima