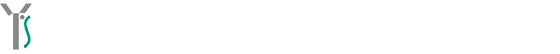真田広之が主演とプロデューサーを務める戦国スペクタクルドラマ「SHOGUN 将軍」の特別上映会がニューヨークのジャパン・ソサエティーで開催され、エグゼクティブ・プロデューサーのジャスティン・マークス氏とレイチェル・コンドウ氏、プロデューサー兼「吉井虎永」役の真田広之氏、「戸田鞠子」役のアンナ・サワイ氏、プロデューサーの宮川絵里子氏が登壇した。
舞台は天下分け目の戦い前夜にある1600年の日本。ジェームス・クラベルのベストセラー小説「SHOGUN」を原作とした本作は「トップガン マーヴェリック」の原案を手掛けたジャスティン・マークスらハリウッドの製作陣の手で映像化され、撮影はカナダでおこなわれた。主人公「吉井虎永」役を演じる真田広之は自身初のプロデューサーを務め、「ラスト サムライ」以降20年間の時代劇への想いを込めて“本物の日本”にこだわった作品だ。そのこだわりの一つとして、歩き方や座り方などの時代と身分に適切な立ち振る舞いができるよう主要キャストだけでなく数百人のエキストラも所作指導を受けたという。テレビ業界の賞レースで新しい顔として存在感を見せるディズニー傘下の製作スタジオ「FX」の最新作ということでも注目を集めている本作の製作に関わるキーマンたちに話を聞いた。
“日本人の目線を散りばめた作品です”
―真田広之
―初のプロデューサーとしてのチャレンジは?
真田広之(以下、真田):初めてプロデューサーとして関われたということがチャレンジでした。いち俳優として限界を感じていた時にプロデューサーというタイトルをいただき、日本からクルーを呼んで時代劇専門の経験豊富なプロフェッショナルを各パートに配置できたことですね。それをハリウッドのスタジオが認めてくれたということも大きなステップになる気がしています。

真田広之氏
―日本人のスタッフが多いと感じました。
真田:これは最初から条件のようなもので、日本人役には日本人を必ず起用してくれと。ネームバリューを優先して“顔がアジア人だったら何人でも良い”という風習は、もうこの時代では終わらせなければいけないという思いがあったので、徹底しました。とにかくオーセンティックに作ることを目指して、海外のお客さんにも分かりやすく、かつ日本の時代劇ファンにも認めてもらえる、その微妙なバランスをうまく取ろうということが狙いでした。
―プロデューサーとして意識したことは?
真田:日本から来たキャストやクルーは初めての海外撮影という人が多かったので、言葉や習慣の違いなど、自分が初めて海外に飛び込んだ時に感じたことを彼らも直面するだろうな、ということが分かっていたので、先行して説明したりコミュニケーションの場を作ってできるだけメンタルのケアもしようというのが、自分の役割でもありました。

©2024 FX Networks
―多国籍の製作陣との間で深くディスカッションしたことは?
真田:まずはジャスティンと、原作を元にどういう方向性で2024年バージョンの脚本を作ろうか、と話し合いました。とにかく海外目線の日本ではなく、ステレオタイプな出来事やセリフ、行動を削っていって。日本人のレンズを通して見えた英国人航海士であり、ポルトガルの宣教師であり、日本から見た世界も取り込もうと。“両サイドからの視点を入れる”というのが今回の一番のオリジナリティーです。
ジャスティン・マークス(以下、マークス):ヒロさん(真田広之)と初めて会った時“この先の未来のためにも日本の文化を間違えて伝えないように”という話をよくしました。言語や歴史的文化、衣装、全てにおいて専門家を付けるように、と彼からアドバイスを受けたんです。本物に近いものを届けるために、どんなに小さなディテールにも気を遣いました。
レイチェル・コンドウ(以下、コンドウ):私たちアメリカ人が本物に近い日本を作る上で、真田さんや絵里子さんのようなコラボレーターは必要不可欠な存在だったんです。色々と教えてもらいながら多くのことを吸収しましたし、その過程はとても有意義で学びがありました。

左からレイチェル・コンドウ氏、ジャスティン・マークス氏、宮川絵里子氏 ©Ayumi Sakamoto
―その中で譲歩したことなどは?
宮川絵里子(以下、宮川):譲歩でいうと、立て膝。歴史家の人の多くは、当時の女性は立て膝をして座っていたといいますが、海外の視聴者には少し違和感があるようです。日本の観客も世界の観客もいる中で“立て膝の女性だと気が散ってしまうのではないか”などのディスカッションを重ねた上で、お城の中では綺麗な正座をして、村のシーンでは少し立て膝も見せる、みたいな。観客が、いかに世界観の中に良い形で入っていけるかという話し合いはありました。お互いにリスペクトがあって、オープンで、ディスカッションを重ねて一つずつ決められたのは、このチームの素晴らしいところですね。

©2024 FX Networks
―印象的なシーンや瞬間は?
真田:論議をしながら物事を選んで決めて、それがバシッとシーンにハマった時ですね。あとはモニターでチェックしながら、俳優さんたちが良いパフォーマンスをしてくれて、製作陣も監督もみんな「これだね!」と満場一致でOKが出た時の「よっしゃー!」っていう、なんとも言えない喜びと言いますか。日本から来た俳優陣が本領を発揮して、このドラマにしっかり焼き付けてくれた瞬間というのはもう、自分のパフォーマンスを褒められるよりも幸せで。あの喜びの深さと衝撃は本当に貴重な体験でした。
マークス:ネタバレにならないように話さないといけないですけど、僕の好きなキャラクターが死を迎えるシーンですね。この日の撮影はとても辛くて悲しかった。この日が最後の撮影日だったので。
コンドウ:細やかな瞬間ですが、小林あきこさん(本作の女性の所作指導も担当)が演じたヒロイン鞠子の侍女「せつ」が部屋を歩いて移動するシーンです。あの深遠な歩き方は誰にも真似できないし、学んでできることでもないと思います。確実に私たちにはないもので、この文化を分かっている人たちとコラボしなければ成り立たないと感じた瞬間でした。

©2024 FX Networks
“とにかく続けること。力尽きたらそこがゴール”
―真田広之
―製作を終えて感じることは?
宮川:日本を舞台とした時代劇がハリウッドのチームによって作られるという経験が初めてだったので、どのような作品が完成するのか漠然としていました。ものすごく宣伝も頑張ってくださっていて、たくさんの方から高い評価を頂いていたり、ここまで期待の高い作品になるとは思ってはいなかったので本当に感無量です。
真田:「ラスト サムライ」以降の20年間で学んだことを全て注ぎ込んだ作品です。まだ完璧ではありませんし、この先の課題も見えました。とにかく作り続けて時代を変えてゆき、こういう作り方がニューノーマルになって欲しいという想いがあります。異文化を扱う時にはちゃんとそのスペシャリストを雇わなければ恥ずかしいよ、という時代にしたいんです。

©2024 FX Networks
―“この先の課題”とは?
真田:その時その時のベストを尽くしても、もうちょっと時間があればとか、もうちょっと予算をかければとか、色々と細かいことが多いので、それをいかに事前に予測して準備できるかということです。
ー真田さんのゴールは?
真田:俳優として、とにかく続けてゆくこと。この歳でやっと手の届く役もいっぱいありますので、そこにおいてはデビュー戦ですから、今まで通りドキドキハラハラしながら続けてゆくことです。それから今回初めてプロデュースをして今までにない面白さや喜びを感じましたので、チャンスがあればプロデュースも続けて、日本の素晴らしい題材、人材、美学を世界に発信できればいいなと思います。一作、二作では時代は変えられないので。何がゴールというよりも、続けていって力尽きたところがゴールみたいな感じです(笑)
―真田さんにとっての“武士道”とは?
真田:日本人の根底に流れている礼儀であり、現代では貫きにくい健常の美徳とか犠牲の精神、誰かに支えるということですね。そういったものをこのドラマから感じ取っていただきたい。武道を通して学んだ“自分に厳しく、人に優しく”というのを現実の生活に活かせることって多分にあると思うんです。そう言った想いがこの製作過程を通して強まりましたし、世界に発信できたらと思っています。

©Ayumi Sakamoto
「SHOGUN 将軍」は、アメリカではHulu、日本ではDisney+
Text: Megumi Hamura