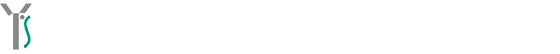President & CEO
河辺輝宏(かわべ・てるひろ)
Morinaga America, Inc
4 Park Plaza, Ste 750 Irvine, CA 92614
1991年、森永製菓入社。関西圏および関東圏の菓子営業、本社菓子食品営業部を経て2008年、国際部アジア・パシフィック担当マネージャーに就任。10年、東南アジア支店長としてシンガポール赴任。12年、米国森永製菓の取締役副社長としてアメリカ駐在、「ハイチュウ」の販路開拓に努める。インドネシアの合弁会社社長、森永アジアパシフィックの代表取締役社長などを歴任し22年、米国森永製菓の代表取締役社長として2度目のアメリカ駐在。23年から米国総代表。お気に入りの「ハイチュウ」はグレープ味。
全米規模の販売網を強みに、 さらなる商品をアメリカで展開
アメリカで今、最もポピュラーな日本のお菓子といえば「ハイチュウ(HI-CHEW)」だ。全米の小売店における取り扱い率は約80%、2023年の売上高は191億円にも及ぶ成功の背景には、柔軟なマーケティング戦略とMLB(メジャー・リーグ・ベースボール)との親和性があった。
ー アメリカ進出のきっかけは。
アメリカ法人を設立する前から日系の商社を通じて、日本人が多いハワイの他、本土の一部地域でも日系やアジア系のスーパーで「ハイチュウ(HI-CHEW)」を販売していました。ハワイのセブンイレブンで「ハイチュウ」の売り上げが好調だったため、2000年代半ばごろから西海岸の店舗にも置いていただけるようになったのをきっかけに08年、カリフォルニアに米国森永製菓を設立しました。
ー 会社設立から6年目でMLB球団のスポンサーに。
進出当初、「ハイチュウ」は主に日系やアジア系のスーパーで販売されており、米系の小売店にもありましたが、アジア食品の売り場に並んでいました。キャンディーは西洋菓子であるにもかかわらず、わさびやのり、しょうゆ、パン粉と同じ棚で「日本のお菓子」として扱われていたのです。販売を最大化していくためには、アメリカのキャンディーブランドの1つとして確立し、キャンディー売り場に並べる必要がありました。しかし、どの店のバイヤーにサンプルを持って行っても、「おいしいね」と言っていただけるのと同時に「他の店が並べたらうちも考える」と返され、この壁を切り崩すことがなかなかできませんでした。 そんななかで、当時MLBのボストン・レッドソックスに所属していた田澤純一選手がブルペンに「ハイチュウ」を持ち込み、選手たちの間で大人気になったのです。これをきっかけにレッドソックスにサンプルを提供する機会を得て、後に球団側からスポンサーシップを結びたいとの申し出をいただきました。アメリカのプロスポーツは地域に根付いた活動が基本で、例えばレッドソックスの場合はアメリカ北東部ニューイングランド地域内のここからここまではマーケティングに球団ロゴが使える、などの権利があります。まだ知名度の低い日本の会社がMLBの有名球団のスポンサーになれるはずがないと思いましたが、地域を限定したスポンサーシップ活動であれば可能な話です。ご存知の通り、アメリカは日本の25倍の国土を持ち、多種多様な人々が集まります。当然人々の趣味や嗜好も異なりますが、全米で同時にマーケティングを行えるほどの会社規模ではなかったので、地域ごとのマーケティングのほうが私たちには合っていました。
 今後のブランディングについて、「2030年までにウェルネスカンパニーへ生まれ変わるという目標を掲げており、これをアメリカでも成し遂げたいと考えています」と語ってくれた河辺氏(提供写真)
今後のブランディングについて、「2030年までにウェルネスカンパニーへ生まれ変わるという目標を掲げており、これをアメリカでも成し遂げたいと考えています」と語ってくれた河辺氏(提供写真)
ー マーケティング活動の内容は。
メーカーがターゲットにするのは末端の消費者であり、B2Cのマーケティングが一般的ではありますが、キャンディー売り場という販売網の開拓段階においては流通、つまりB2Bの視点で動くことが先決だと考えました。そこで、レッドソックスの他にシカゴ・カブス、ミネソタ・ツインズともスポンサーシップを組みました。なぜこの3球団かというと、レッドソックスはドラッグストア大手「CVS Pharmacy」の本社、カブスはドラッグストア大手「Walgreens」の本社、ツインズは小売大手「Target」の本社がそれぞれ本拠地の近くにあり、それらの小売業の幹部やバイヤーの方々も「ハイチュウ」ブランドに触れる機会が多くなるだろうと考えたからです。 例えば、レッドソックスの本拠地であるフェンウェイ・パークでサンプルを配ったり、「ハイチュウ」の名を冠したアクティビティーを提供したりして地元のファンの間に浸透していけば、「CVS Pharmacy」でもキャンディー売り場に「ハイチュウ」を置いていただけるようになる。この流れで、「ハイチュウ」を本気でアメリカのブランドとして展開していくために、B2Bで攻めていきました。これらの活動が実を結び、全米規模の店としては初めて、「Walgreens」のキャンディー売り場に「ハイチュウ」を並べていただくことが叶ったのです。これに続き、「Walmart」「Kroger」「Albertsons」など小売チェーン大手のキャンディー売り場にも置いていただけるようになりました。 「ハイチュウ」の成功はMLBのおかげだと思われがちですが、どちらかというとそれは副次的なものであり、このビジネスの肝はやはりアジア食品からキャンディーへと販売網を変換していったところにあります。地域のファンの心に刺さる活動というよりも、「『ハイチュウ』は地元の人気チームとスポンサーシップを組んでいますよ。地元のお客様のために『ハイチュウ』を扱ってくださいね」というアプローチです。
ー その他のスポンサー実績は。
MLBでは先ほどの3球団の他にロサンゼルス・ドジャース、またNBAのニューヨーク・ニックスともスポンサーシップを組んだことがあります。MLBの選手たちは「ハイチュウ」のロゴ入りTシャツを着てSNSに写真をアップしてくれることもありましたが、NBAの試合はキャンディーを食べる雰囲気ではないのか、残念ながら選手内で「バズる」ことはありませんでした。「ハイチュウ」は野球独特のまったりとした、ファミリーフレンドリーな雰囲気と親和性があるように感じます。
ー 市場規模と商品開発のポイントは。
アメリカで「ハイチュウ」はノンチョコレートというカテゴリーに属し、市場規模は約110億ドルと莫大です。アメリカの1人当たりのキャンディーの消費量は日本の4倍に及び、この差は特定の層がたくさん消費しているからではなく、子どもからお年寄りまであらゆる層が消費していることに起因します。形態にしても日本ではスティックパックか小袋ですが、アメリカではそれらに加えて850グラム入りの大袋もあります。また、日本ではストロベリー、グレープなどシンプルなフレーバーが好まれますが、アメリカでは多様なフレーバーが好まれ、例えば「ブルーラズベリー」や「ブルーハワイ」などが普通に受け入れられるところが日本との大きな違いです。複数のフルーツの組み合わせや、カクテルとフルーツの組み合わせといったユニークなフレーバーの商品を開発し、販路拡大の努力とともにお客様の受け入れやブランドに対する期待などにもしっかりと向き合うために、消費者調査もマーケティング部門で真剣に行ってブラッシュアップして参りました。社会のニーズに沿った商品も順次開発しており、人々の健康志向に応じた低糖質の商品や、環境に配慮して包装のプラスチック量を減らした商品もあります。
ー アメリカで評価される理由は。
「ハイチュウ」に関しては、豊かなフレーバーと食感です。アメリカで人気のグミにも似た、噛みごたえがありながら歯にくっつきにくい食感が受け入れられています。 日本のお菓子とアメリカのお菓子の違いという点では、一般的に日本のお菓子は繊細でプレミアムだと見なされています。私たちも日本でさまざまな商品や技術を開発してきましたが、日本ならではの繊細さが結果として認められているのだと思います。しかしながら、お菓子に限らず日本の商品は「ガラパゴス」なところがあり、繊細すぎてその良さが分かっていただけない部分もあります。例えば開封しやすいようにデザインされた菓子箱のミシン目は、この繊細さこそが日本のクラフトマンシップであり、アジア圏では「さすが日本だ」となりますが、アメリカではお菓子はおいしく食べられればいいわけで、開け方などはさほど重要ではないようです。
ー アメリカの売り上げについては。
「ハイチュウ」に限って言えば、アメリカは海外事業全体の80%強と圧倒的で、市場の大きさを実感します。以前からアジア圏でも「ハイチュウ」を販売していますが、アメリカの消費量は桁違い。ニュージーランドやオーストラリアでもアジア食品からキャンディー売り場に移り、どんどん売り上げが伸びていった実績があるため、西洋文化圏では受け入れられる可能性が非常に高いです。欧州にも進出しており、これから確実に伸びると見込んでいます。 なお、アメリカ国内では売り上げのほとんどを「ハイチュウ」が占めていることから、メーカーシェアという意味ではノンチョコレートカテゴリーのなかで1.2%のシェアを占めています。トップのメーカーシェアが12%ほどで、これからもっと追いつける余地はあると思います。
 シカゴ・カブスの本拠地、リグリー・フィールドでのサンプリング活動(提供写真)
シカゴ・カブスの本拠地、リグリー・フィールドでのサンプリング活動(提供写真)
ー 今後の目標は。
最初の駐在は「ハイチュウ」をアメリカのキャンディーの販売網に乗せることがミッションで、一定の成果を上げることができました。そして今回は、前回のノウハウおよびキャンディーの販売網を全米規模で持っていることを強みに、さらなる商品をアメリカで展開していくことを目標としています。2022年には、ドリンクタイプのエナジージェル「チャージェル(Chargel)」を発売しました。このようなエナジージェルドリンクはアメリカにはほとんどなく、「ハイチュウ」同様に草の根活動から始めなければいけませんが、積極果敢にスポーツイベントでサンプリングを行っています。また23年には、日本でロングセラーのキャラメル「ハイソフト(HI-SOFT)」をアメリカで発売しました。既に取引がある「Walmart」のバイヤーに直接持ち込みましたが、これは日系菓子メーカーでは今のところ私たちにしかできないことです。このように、日本で持っているブランドをアメリカ向けにカスタマイズして、順次拡大を目指しているところです。
Editor : Miho Kanai
※「シカゴ・デトロイト便利帳 Vol.21」でのインタビューを再編集して掲載
2023年12月29日取材

▼本誌掲載
ニューヨーク便利帳 Vol.33